過払い請求の裁判の必要書類の作り方
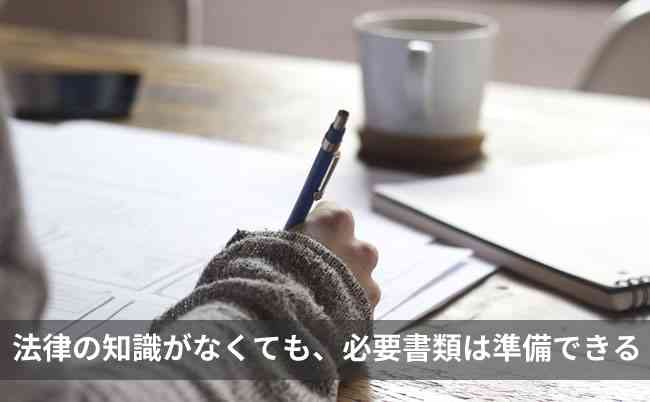
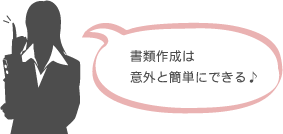
裁判をするために準備する書類(添付書類含む)は以下になります。
訴状
訴状は、正・副(裁判所用と貸金業者用)、あわせて2部作成し、裁判所に提出することになります。
裁判の時、自分の手元にも控えがあると良いと思うので合計3部作っておくとよいでしょう。
訴状の内容は大きく分けて、4つになります。
- 当事者の表示
- 請求の趣旨
- 請求の原因
- 証拠方法
「当事者の表示」とは、原告・被告が誰であるのかということを書きます。
被告となる貸金業者については、会社名だけでなく代表取締役の名前まで書きます。
例: ○○○株式会社 代表取締役 △△△ △△
「請求の趣旨」には、原告であるあなたの要求を書きます。
ここで書く要求内容とは、以下の二点になります。
- 過払い金に年5%の利息をつけて支払え
- 訴訟費用は被告の負担とする
「請求の原因」は、請求の趣旨を補足するもので、なぜこの様な請求をしたのかという理由になります。これを具体的に書きます。
「証拠方法」とは、上記の主張を証明する証拠の一覧を書きます。
訴状を白紙の状態から書くとなると、書式や内容など分からない・・・となってしまいますが、テンプレートを用意していますので、ご自身の状況(相手となる貸金業者の名前・過払い金の額、その他日付など)にあわせて、空欄箇所を埋めていくようにすれば簡単に訴状を作ることができます。
証拠書類
証拠書類として準備するのは、今までの過払い請求に使用したものばかりです。
- 取引履歴
- 引き直し計算をしてプリントアウトしたもの
- 過払い請求返還請求書
- 過払い請求返還請求書を送付した際の配達記録
これらのコピーを取ります。
準備するのは、訴状の正・副に添付するため2部になります。
これらの証拠には、通し番号を振らなければなりません。
証拠書類の右上に赤文字で「甲第○号証」と書いてください。
裁判所へ提出する際は、証拠書類の原本も持って行かなければいけません。
代表者事項証明書
必要な代表者事項証明書は、1通です。
最寄りの法務局へ行って取得します。
法務局へ行くと、「登記事項証明書 交付申請書」という書面が備え付けてあります。
必要事項を記入し、収入印紙(600円)を貼り、提出します。
※収入印紙は、法務局内で販売しています。
収入印紙
これは、訴額(貸金業者に請求する過払い金と利息の合計金額)によって変わってきます。
下記の表を参考にしてください
| 訴額 (万円) |
印紙代 | 訴額 (万円) |
印紙代 | 訴額 (万円) |
印紙代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,000円 | 120 | 11,000円 | 320 | 21,000円 |
| 20 | 2,000円 | 140 | 12,000円 | 340 | 22,000円 |
| 30 | 3,000円 | 160 | 13,000円 | 360 | 23,000円 |
| 40 | 4,000円 | 180 | 14,000円 | 380 | 24,000円 |
| 50 | 5,000円 | 200 | 15,000円 | 400 | 25,000円 |
| 60 | 6,000円 | 220 | 16,000円 | 420 | 26,000円 |
| 70 | 7,000円 | 240 | 17,000円 | 440 | 27,000円 |
| 80 | 8,000円 | 260 | 18,000円 | 460 | 28,000円 |
| 90 | 9,000円 | 280 | 19,000円 | 480 | 29,000円 |
| 100 | 10,000円 | 300 | 20,000円 | 500 | 30,000円 |
例を挙げると、
- 訴額が150万円であれば、13,000円分の収入印紙が必要。
- 訴額が100万円の場合は、10,000円分の収入印紙が必要。
- 訴額が50万円の場合は、5,000円分の収入印紙が必要。
予納郵券(切手)
予納郵券とは、切手のことです。
裁判所が原告であるあなたや、被告となる貸金業者宛に書類(訴状や答弁書など)を郵送するのに使用します。
実は提出先の裁判所によって必要な金額と内訳が変わります。
ですので、事前に訴状を提出する裁判所に電話をかけて切手の必要枚数を確認しておきましょう。
管理人が行った裁判所では、総額6,400円分でした。
どこの裁判所でもだいたい5,000~7,000円ほどかかります。
ちなみに内訳は下記の通りでした。
| 金額 | 枚数 | 金額 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 500円 | 8枚 | 270円 | 2枚 |
| 200円 | 2枚 | 100円 | 8枚 |
| 80円 | 2枚 | 50円 | 4枚 |
| 20円 | 10枚 | 10円 | 10枚 |
※使用しなかった切手は裁判が終わった段階で裁判所から返してもらえます。